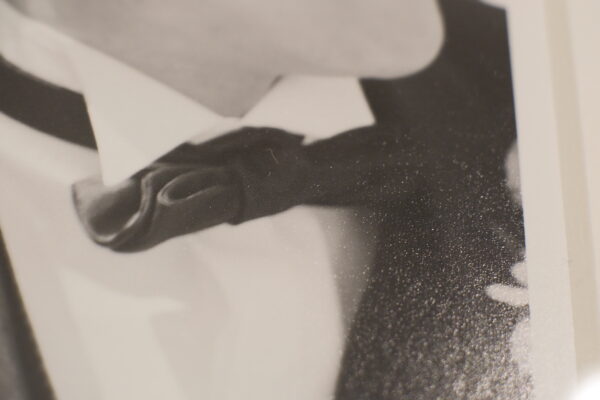先日、Leica M11とSummilux 35mm f1.4 FLE2(11726)を購入した経緯を紹介しました。
しかし中古カメラ店で初めてライカのオールドレンズを見た際に感じた、造形の凄みや歴史的な製品群への憧れがどうにも忘れられず、悶々とした日々を過ごしていました。レンズ開発の歴史やレンズの描写・造形を調べだすとキリがなかったのですが、考えが巡り巡った挙句Summilux 50mm f1.4 (1st)を購入しました。
今回は、手持ちの35mmとの差別化として50mmに絞り、「Summarit 5cm f1.5」と「Summilux 50mm f1.4(1st & 2nd)」を候補に、実際に店頭で試写した体験を記します。
SummaritとSummiluxの試写比較:写りの癖と魅力
製造の背景を辿るに、これら二つは兄弟レンズとのこと。特許等の兼ね合いにより、先代Xenonから時代を下って発売されたものがSummarit、そしてSummiluxだそうです。Summiluxには複数の世代があることも魅力の一つですが、その中でもオールド味を感じられる1st、2ndに狙いを定めて行きました。製造からの月日が長いためにレンズ個体差が大きいらしく、世代差・個体差が素人目にどの程度影響するか判断しかねたので試させていただきました。

まずは簡単な所見から。
Summarit 5cm f1.5(Mマウント前期)は、造形では最も惹かれたレンズでした。
絞り指標部分は光沢ツヤ仕上げで、円形の絞り羽根も見事な造形。鏡胴溝の彫り込みと距離指標部分のくびれ、所々のビス留めなど工芸品チックさが美しく、見た目ではナンバーワンでした。自宅に飾りたいくらい。
ただ、試写してみると、半逆光程度でもゴーストが出現し、全体的なコントラスト低下が見られました。「これはこれで楽しい」と思う反面、「自分の力量で扱い切れるか?」という不安が正直ありました。
次にSummilux 50mm 2ndを試写。(作例なし)
こちらは開放でもコントラストが高めで、中心部のシャープさにも安心感がありました。オールドといえど、実用性を求めるなら選ばれそうな一本でした。個人的にはもう少しクセがあるものを求めていたためにパス。
最後にSummilux 50mm 1stを装着。
ローレットの加工や、反光沢の渋いシルバー仕上げも格好いいです。描写は2ndよりも柔らかく、絞り開放時ではピント面が結像していてもぼんやりした写りです。そしてハイライト周辺にうっすらと滲むようなグロー感があり、これが情緒的な雰囲気を一層際立たせます。一方でF2.8以降ではピント面もシャープで、二面性を活かすことができそう。古いレンズらしい描写のクセはありながらも、Summaritほど極端ではなく、自然に写真に馴染む雰囲気がありました。




Summilux 50mm f1.4 1stをM11に装着|描写と作例紹介
■ 外観
購入後すぐ、Leica M11に装着してみました。装着したときの見た目の美しさに思わずニヤけてしまいます…。
鏡胴はほんの少し経年の味が出ていて、シルバークロームの質感がたまらない。「貴婦人」とも呼ばれるこのレンズ、たしかにどこか品がある、ような?。現代レンズのような完璧さとは違う、クラシックな工芸品のような佇まいに、使う前から気持ちが高まります。



レンズフィルターには、Mapcameraにて販売されている「M.I.Star 43mm」を装着しています。前玉の膨らみにより、一般的な43mmフィルターでは装着できない場合があったり、純正のレンズフードが干渉するようなのでご注意を。純正フードXOOIMだけで2〜3万円もする世界です…。
⸻
■ 作例と描写
いくつか試し撮りをしてみたので、その作例を紹介します。
開放F1.4の描写
ピント面にはじんわりとした芯がありつつ、背景は柔らかいボケ。
とくに気に入ったのは、光が当たった被写体の立体感。ハイライトに滲みが生じることで、光の輪郭がやさしく包んでいるように写ります。開放でも「甘いだけ」ではなく、光を捉える力強さもありました。
二枚目の“福建会館“を駆け上がる写真では、少年少女時代を懐古するような出来上がりになっています。総じて、ぼんやりとした光がドラマチックな表現を手助けしてくれたことで、懐かしむ際の感情を呼び起こすのに一役買いそうです。



F2.8〜F4まで絞ったとき
シャープさがぐっと増し、安定した描写に。色のりも良好で、現代的な描写とレトロ感の中間地点のようです。
赤いランタンの写真では、ランタンからの光に負けず、文字もハッキリ描写していますね。日常スナップでは、開放のみならず少々絞ることで、被写体の空気感を保ちながら、記録性も持たせることができる。「味」と「実用性」のバランスがとても良いという印象です。とはいえ、せっかくの大口径が勿体無いので、もっぱら開放で使用しています。
なお2枚目の工事現場の夜景では、点光源の口径色もご確認ください。



⸻
■ 撮っていて気づいたこと
逆光ではゴーストが出るけれども、それも個性として許容できるレベルでした。
また、開放ではときおりグルグル感あるボケが現れる場面もあり、被写体や背景によって絵の表情が変わる点も面白いです。時折、開放時のピント面の甘さから「距離の見立てを間違えたか?」と不安になることもありますが、レンズの特性または自身の手ぶれが原因でした。くっきり解像させたい場合は一段以上絞って使用しています。
使い分けの贅沢な悩み
Summilux 35mm f1.4 FLE2(11726)と、50mm 1stは、まったく異なる描写傾向。11726が「現代ライカのシャープネスを持った情緒レンズ」なら、50mm 1stは「滲みで魅せるノスタルジックレンズ」とでも言いましょうか。
元来私はSummiluxの情緒的な写りが好みのため、M11とSummilux 50mm 1stの組み合わせで、これからどんな写真が撮れるか楽しみでなりません。今後はこの2本のレンズをどういう場面で使い分けるか、じっくり紹介していきます。